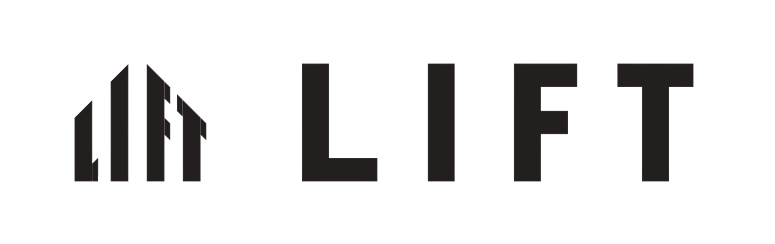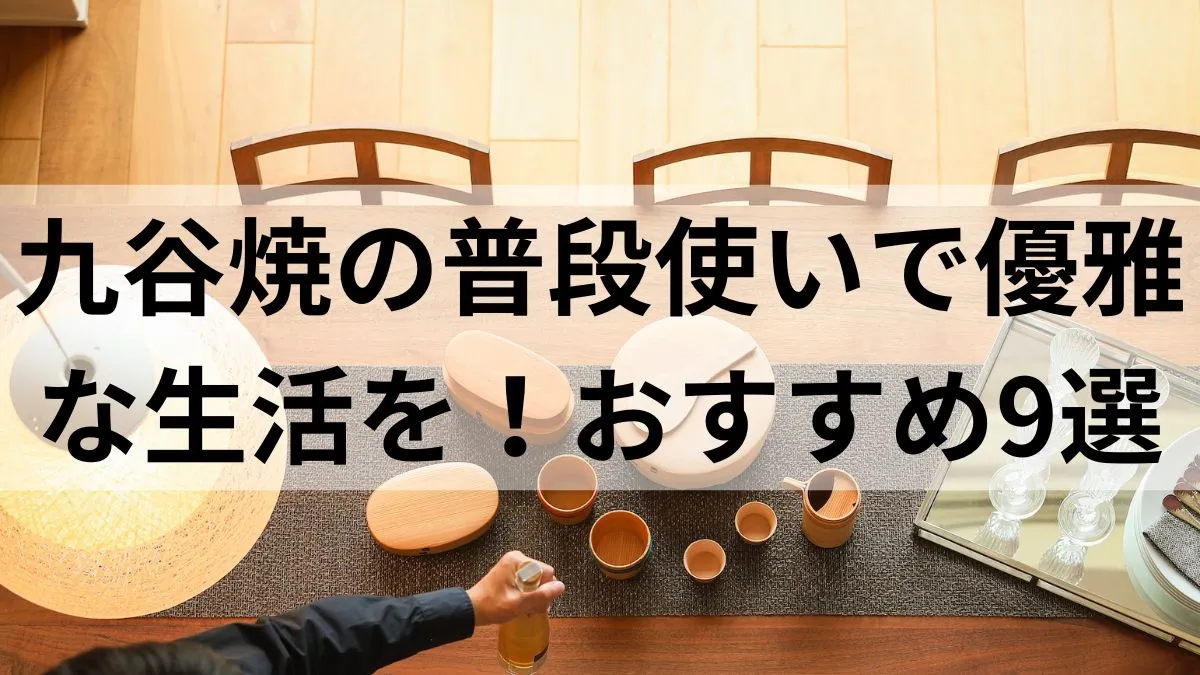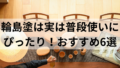和食器のある生活にあこがれている方なら、一度は試してみたい九谷焼。
華やかな絵付けの美しさに惹かれるものの「食洗器や電子レンジは使えるの?」「初心者にも使いやすいお皿はあるの?」と思う方もいるでしょう。
この機会に、ぜひお好みの九谷焼を見つけてくださいね。
和食器レンタルサービス「LIFT」では高品質な九谷焼を手軽に月額レンタルできます。
5ヶ月間継続利用すると6ヶ月目から無料であなたのものに。
「九谷焼を普段使いしたいけれど、値段が高くて買うには抵抗がある…」という方は一度ぜひお試しください。
\ 全品新品!1か月単位でお試しできる /
和食器をレンタルするなら「LIFT」
九谷焼の特徴とは?技法の種類一覧
九谷焼は、明治20年代に陶磁器輸出貿易額の第1位を誇り「ジャパンクタニ」として世界に名が知られました。
ここではその九谷焼の特徴的な技法と、それぞれの種類ごとに、おすすめの使い方について解説します。
| 九谷焼の技法 | 特徴 | 普段使いにおすすめの皿 |
| 赤絵細描 (あかえさいびょう) |
細い筆で赤絵を描く技法 髪の毛ほどの細さの線を、幾重にも重ねて浮かび上がらせる、九谷焼の代表的な伝統技法で、海外で名が知られる「ジャパンクタニ」は主にこの赤絵細描を指します |
平皿(円いお皿) 赤絵の美しい模様が額縁のように食事を縁取ります。 和洋中を問わず使えるため、チャーハンやパスタなど一品料理を盛るのにおすすめです |
| 青手 (あおで) |
緑色や黄色を用いた技法 青手は赤色を使わず、主に九谷独特の深みある緑色・黄色を用いて作製した器を指し、古九谷の頃から使われている技法です |
刺身皿や小皿 皿の全面に施された色彩を楽しむために、絵柄を引き立てる刺身皿や菓子用の小皿として使うのがおすすめです |
| 五彩手 (ごさいで) |
九谷五彩を用いた様式 九谷五彩とよばれる黄・緑・紫・紺青・赤色を用いた様式で、古九谷の頃から伝わる技法。花鳥風月の絵柄が代表的です |
ご飯茶碗 鮮やかな五彩と、花鳥風月の風流な絵柄が楽しめます。 五彩が映えるご飯茶碗が普段使いにおすすめです |
| 金彩 (きんさい) |
金の加飾を施したもの 金箔の上に透明な釉薬をかけた釉裏金彩、赤絵に金の加飾を組み合わせた赤絵金彩が有名です |
釉裏金彩はぐい呑み、赤絵金彩は深皿椀 透明感のある金の風合いが美しい釉裏金彩は、優雅なぐい呑みに。 豪華な縁取りが美しい赤絵金彩は、汁物の深皿椀がおすすめです |
| 粉引 (こひき) |
粉を引いたように白い器 土のぬくもりを感じる素地に、白泥の化粧をかけて仕上げたもの |
カップ&ソーサ― コーヒーの色が白い器に映えるカップ&ソーサーがおすすめです |
| 染付 (そめつけ) |
藍色の絵付を施したもの 白磁の器に藍色の絵付がよく映えます。 染付は有田焼や清水焼などが代表的ですが、九谷の染付は繊細なタッチの筆づかいが優美です |
角皿 食材の色を邪魔しない染付は、豪華な煮魚を一尾のせたり、お漬物をちょっとのせるのにもぴったりの角皿がおすすめです |
九谷焼は技法によって器の風合いが異なるため、ご自宅の雰囲気やプレゼントする方の趣味にあわせて、お好みのものを購入するとよいでしょう。
九谷焼の使いやすさはどう?普段使いできる?
九谷焼は、古くからの伝統と実用性を兼ね備えた便利な器です。
電子レンジや食洗機も、ポイントさえおさえれば使用できるため、日常使いにもおすすめです。
食器を購入する前にこちらをチェックして、使いやすい九谷焼を選んでくださいね。
電子レンジは使用できる?
それは、金銀の細工がレンジ庫内で反応する可能性があり、陶器は急激な温度変化に弱いためです。食器をより長持ちさせたい!とお考えの方は、できるだけ食器をやさしく取り扱って、電子レンジの使用頻度を控えましょう。
食洗機は使える?
ただし、軽く薄い小皿などは、食洗機の水圧で小皿が動いて傷つくおそれがあるため、手洗いをおすすめします。
食器が食洗機内で動いた際に細工に傷がついたり、温度変化で食器が割れる可能性があるため、これらの食器の食洗機使用は控えましょう。
普段のお手入れは大変?
九谷焼は普通の食器用洗剤とスポンジで洗えますし、普段のお手入れも簡単です。
できるだけ食洗機を使わずに手洗いをこころがけて、食器棚に保管するときに擦れるのが気になるときは、やわらかい紙をはさみましょう。
少しだけ丁寧に取り扱うだけで、九谷焼の器は問題なく日常に取り入れられます。
九谷焼はデリケートだから、割れないように気を付けなければ……と肩肘はらずとも、ちょっとしたルールを守ればお手入れは簡単です。
絵柄が多くて使いにくい?
九谷焼は豪華絢爛な絵柄が多いため、使いにくいのでは?と感じる方もいらっしゃるでしょうが、そんなことはありません。
確かに九谷焼の絵柄はカラフルで個性的ですが、だからこそアクセント使いすることで、食卓の雰囲気をパッと華やかにできます。
九谷焼を初めて使うという方は、いきなり大皿などを買わずに、小皿や箸置きなど使いどころがはっきりした食器を買うとよいでしょう。
九谷焼で人気の柄は?かわいい絵柄やモダンな絵柄はある?
ここでは九谷焼で人気の、かわいい絵柄の器やモダンな絵柄の器をご紹介します。
| 人気の絵柄 | 絵柄の解説 | 画像 |
| 赤絵小紋 | 小紋は、模様がお皿全体にまんべんなく施され、上下左右の向きを気にせず使用できるため、モダンな雰囲気で普段使いにおすすめです |  |
| 古九谷風 | 器の全面にほどこされた、彩り豊かな五彩と青手が、食卓にほどよいインパクトを与えます |  |
| 花鳥風月 | かわいい花鳥風月の絵柄が、食卓に華やぎを与えます |  |
| コラボ柄 | ドラえもん、ガンダムなどとコラボしたモダンな絵柄の九谷焼は、プレゼントなどにも人気の作品です |
絵柄によって、食卓に与える印象が異なりますので、ご自宅で器を使用するシーンを想像して、九谷焼を購入するとよいでしょう。
普段使いにおすすめの九谷焼9選
こちらでは、普段使いにおすすめの九谷焼を9種類ご紹介します。
一粒お菓子を盛るのに最適な「豆皿」や、サラダを盛るのにおすすめな「角皿」など、ぜひお好みの九谷焼をみつけてください。
豆皿|一粒お菓子やおつまみのちょこ盛りに派手な柄がおすすめ
仕事や家事で疲れてチョコレートを一粒食べるときに。夜の晩酌のお供におつまみをのせるときに。
袋からそのまま頬張るのもいいですが、おしゃれな豆皿にのせるだけで、リラックスタイムが特別なものへと変化します。
来客の際、ちょっとしたお菓子を盛るときにも便利です。
角皿|サラダや果物を盛るだけで豪華な一品に早変わり
九谷焼の角皿は大きさも形もさまざまですが、共通しているのは器のふちが盛り上がっていて、食べ物が逃げにくいという点です。
そのため、ドレッシングがかかったサラダや、ころころ転がりやすい果物を置いても、食材の汁が流れたり食材が転がり落ちることなく、スムーズに食べられます。
小鉢|おでんや煮物の盛り付けにレンジOKのものがおすすめ
仕事の帰りが遅い日にコンビニで買ったおでんも、上品な九谷焼の小鉢に盛れば、贅沢な夕飯に早変わりします。
汁ものごとレンジで温めたいときに備えて、レンジ使用が可能な金彩が入っていない器を選び、日常使いするとよいでしょう。
普段使いにぴったりの赤絵細描や染付の小鉢がおすすめです。
刺身皿|刺身の身が透ける豪華な赤絵金彩や青手の器がおすすめ
スーパーで購入したお刺身のパック。
そのまま食べてもいいですが、九谷焼の器に盛れば、優雅な夕食の時間が過ごせます。
とくに白身の刺身は、器の絵柄が身から透けて見えるため、器を絵画のように楽しめます。
そのため、豪華な赤絵金彩や器全体に絵がほどこされた青手の器を使うのがおすすめです。
醤油差し|置物のように眺めて飽きない器がおすすめ
醤油差しは日常の食卓の真ん中に置くものですから、どうせならお気に入りの色形のものを選びたいものです。
九谷焼では、色彩豊かなものから、鳥型、ひょうたん型、急須型、シンプルな白い粉引など、さまざまな色形のものを販売しています。
箸置き|楽しい柄で会話が弾む!欠けにくいものを選ぶとなおよし
箸置きは、お箸を置くときに何度も見て触れるため、食卓で重要な役割を果たします。
そのため、見るたびに気分がよくなる派手な柄のものや、家族やご友人との会話がはずむ、楽しい柄を選ぶとよいでしょう。
遊び心あふれる九谷焼の箸置きは、さまざまな種類が販売されていますので、少しずつ買いそろえてコレクションするのも良いでしょう。
ただし、食卓での使用頻度が高く、落下することもあるため、できるだけ丈夫で欠けにくいものをチョイスすると良いでしょう。
徳利と盃|お燗もつけられる!五彩の花鳥風月柄がおすすめ
徳利(とっくり)と盃(さかずき)は、一日のリラックスタイムをゆったり過ごすときに重要なアイテムです。
冷酒がお好きな方は、金彩のあるものを選んでもよいですが、お燗をつける方は、レンジであたためられるものをチョイスしましょう。
例えば、五彩の花鳥風月柄は毎日眺めても飽きのこない絵柄で、金彩がついておらず、レンジのあたためも可能です。
湯呑み|手に熱が伝わりにくい粉引がおすすめ
毎日使う湯呑みは、手に取るときに熱くなりにくい粉引がおすすめです。
九谷焼のほかの磁器に比べて、陶器の粉引は手に熱さが伝わりにくいため、熱いお茶を好む方にはおすすめです。
また、粉引のナチュラルなホワイトは、さまざまなお部屋のテイストにもぴったり合うため、九谷焼をはじめて使う方にもおすすめです。
花瓶|華やかな釉裏金彩でお部屋を彩るのがおすすめ
釉裏金彩は九谷焼独特の技法で、磁器の上に金箔や金泥を貼り付け、その上に釉薬をかけたものです。
釉薬のコーティングで金彩がひときわ輝いて見えるため、一輪挿しをひとつ部屋に置くだけでパッと部屋が華やぎます。
逆に、花瓶の色味をおさえて目立たせたくない方は、粉引や染付など、シックな色合いの花瓶を選ぶとよいでしょう。
九谷焼の使い方とお手入れ方法の注意点
ほとんどの九谷焼は、特別なお手入れの必要がなく購入後すぐに使用できます。
ただし、「土もの」とよばれる陶器(粉引など)は使用前に少しお手入れが必要です。
下記の表に、九谷焼の陶器のお手入れ方法と、使用する際の注意点をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| 購入後の お手入れ |
高台(器の下の高くなっている部分)がざらざらしているものは、テーブルや他のお皿を傷つける可能性があります。
|
| 初回使用前の お手入れ |
表面に貫入(かんにゅう:ひび割れのようなもの)が入っている器は、そこから食べ物の色素が入って色がついたり、水が入ってカビが生える可能性があります。
|
| 使用中の 注意点 |
表面がザラザラしている器は、衝撃に弱いため、金属のナイフやフォークの傷がつきやすいです。強くこすらないようにしましょう。 |
| 使用後の お手入れ |
|
| 収納する際の 注意点 |
陶器は衝撃に比較的弱く割れやすいため、重ねて収納する場合は柔らかい紙を挟むとよいでしょう |
陶器の九谷焼は、上記のように使用前に少しお手入れをする必要があります。
ただ、使用前に一度お手入れをしてしまえば、その後特別なお手入れをする必要はありません。
九谷焼が欠けたらどうしたらいい?
大事な九谷焼が欠けてしまったら、捨てなきゃいけないの?と不安になりますよね。
そういうときは、欠けた食器をよみがえらせる「金継ぎ」がおすすめです。
九谷焼に限らず陶磁器は欠けやすく、丁寧に扱っていても縁(ふち)が欠けてしまうことも多々あります。
少し縁が欠けた程度であれば金継ぎによって、食器が装いも新たに生まれ変わります。
金継ぎは、職人に依頼するのがおすすめですが、初心者でも出来る金継ぎセットも発売されていますので、ご自分で修理したいという方にはおすすめです。
九谷焼に関するよくある質問
ここからは、九谷焼に関するよくある質問に答えていきます。
なんとなく九谷焼は目にしたことがあるけれど「古九谷は九谷焼とどう違うの?」「九谷焼の値段相場は?」など、皆さまのさまざまな疑問にお答えしますので、ぜひ参考にしてください。
九谷焼は陶器?磁器?
九谷焼はほとんどが磁器ですが、粉引など一部の技法を使ったものは陶器に分類されます。
| 特徴 | 九谷焼の技法 | |
| 陶器 |
|
|
| 磁器 |
|
|
九谷焼にはさまざまな技法が用いられているため、購入する食器が陶器か磁器か、区別がつきにくいこともあるでしょう。
古九谷焼とは?どんな特徴?
古九谷焼は1655年~1700年頃までに九谷で制作されたものを指します。
狩野派の影響を受けた絵画的な表現が特徴的です。
古九谷焼は、1655(明暦元)年頃に大聖寺藩の初代藩主が御用窯を開いたのが始まりです。
しかし、この窯は1700年代初頭にいきなり閉窯してしまいました。
その理由は分かっていませんが、この短い期間に制作された作品は、古九谷として後世に色濃く影響を与えました。
古九谷焼には、五彩を使用した大胆な構図のものや、器全体を塗り埋めて赤色を使用しない青手とよばれるものがあります。
古九谷焼の印象的な絵柄は、300年以上経った今でも人気で、さまざまな窯元で古九谷風の作品が制作されています。
九谷焼の人気作家は?有名な窯元は?
九谷焼は300年以上の歴史があり、数々の窯元が設けられ、多くの人気作家を輩出しています。ここでは、九谷焼の人気作家と有名な窯元をご紹介します。
九谷焼の人気作家
| 人間国宝 吉田美統 (よした みのり)釉裏金彩 |
吉田美統は釉裏金彩の第一人者で、平成13年に国指定の重要無形文化財釉裏金彩の保持者に指定されています。 極薄の金箔を自在にカットする唯一無二の技術で、国内外から高く評価されています。 |
| 三ツ井為吉 (みつい ためきち)古九谷五彩 |
三ツ井為吉は古九谷時代から愛されてきた五彩を用いて、伝統的な花鳥柄の絵付けなどを得意としています。 日常使いできる食器から、花器・香炉など幅広い作品を制作しています。 |
| 福島礼子 (ふくしま れいこ)赤絵細描 |
福島礼子は赤絵細描の第一人者である父の福島武山から受け継いだ技法を用いて、細密な赤絵の描写を得意としています。 文様の組み合わせによってモダンに仕上げた赤絵細描の作品は、普段使いにもおすすめです。 ≫福島礼子が手がけた九谷焼の作品をレンタルする |
| 山本長左 (やまもと ちょうざ)染付 |
山本長左は九谷染付の第一人者です。 細かい筆致と大胆な文様の組み合わせ、そして味のある形状の器が特徴的で、伝統のなかにも新しさを感じさせる食器を多く生み出しています。 芸術品のように美しい仕上がりですが、料理を引き立てる食器を中心に制作されているため、普段使いにもおすすめです。 |
| 仲田錦玉 (なかだ きんぎょく)青粒 |
盛金青粒技法の第一人者である仲田錦玉は、小さく等間隔で青粒を描く超絶技巧で知られています。 美術品のような美しさの青粒ですが、仲田錦玉はぐい呑みやカップ&ソーサーなど、日常使いできる作品も制作しています。 |
九谷焼の有名な窯元
| 青郊窯 (せいこうがま) |
青郊窯は、九谷焼独特の五彩を独自の転写システムでプリントすることで、安価な価格で器を販売し大ヒットしました。 特に豆皿は人気商品で、ドラえもんやハイジ、ガンダムとコラボした商品も販売しているため、お気に入りのキャラクターの食器を九谷焼の鮮やかな色彩で楽しめます。 |
| 上出長右衛門窯 (かみでちょうえもんがま) |
上出長右衛門窯は1879(明治12)年創業の老舗の窯元で、彩り豊かな絵付けと丈夫な生地の作品が、長く人々に愛されてきました。 近年は伝統的な絵柄のものに加えて、黄色と黒のコントラストが現代的な「TEA」シリーズなど、普段のティータイムをワンランク上のものにしてくれるおしゃれな急須や湯呑を発売しています。 |
| 清山窯 (せいざんがま) |
清山窯は明治後期創業の歴史ある窯元で、開窯以降伝統を守り続け、食器や生活用品など、日々のくらしに密着した陶磁器を作り続けています。 伝統的な古九谷風の絵柄の平皿や、染付のカップ&ソーサーなどが普段使いにおすすめです。 |
| 錦山窯 (きんざんがま) |
錦山窯は1906(明治39)年に創業した窯元で、人間国宝 吉田美統が作陶しています。 釉裏金彩の輝きが美しい盃や、繊細なグラデーションと金の細工が美しい「浮世」シリーズなどを食卓に取り入れれば、日常が優雅なものに変化するでしょう。 |
| ハレクタニ | ハレクタニは伝統的な九谷焼を現代風にアレンジし、北欧風の絵柄の作品を多く手がけています。 日常使いに便利なスープボウルや、正方形の形がモダンな角プレートなどがおすすめです。 |
九谷焼の5色と言えば何色?
九谷焼を代表する5色は、紺青・緑・黄・赤・紫を指し「九谷五彩」とよばれています。
五彩の中で赤色を使用しないものを「青手」とよび、逆に赤色のみを用いて制作した作品を「赤絵」とよびます。
ジャパンクタニとよばれ海外で愛された九谷焼は、細かい筆致の赤絵細描の作品を指します。
長い冬に雪で覆われる九谷の地域では、色とりどりの五彩を眺めて彩りを感じていたと言われ、九谷五彩の器が重宝されました。
九谷焼が誕生して300年以上経った今でも、華やかな九谷五彩は人々に愛され続けています。
九谷焼の値段の相場はどれくらい?
九谷焼の価格の相場は数千円~100万円台と大きな開きがあります。
なぜここまで開きがあるのか?
それは「器の大きさと形」と「手作業の細かさ」に起因します。
器の大きさと形による九谷焼の価格相場の違い
九谷焼の値段は、器の大きさと形によって価格が変動します。
小さなぐい呑みなどであれば2万円代壺や花瓶、大皿など大型の器は、作陶に時間がかかるためその分値段が高くなります。
また香炉や花瓶など形が複雑な器は、生地の成形に時間がかかり、また絵付けがしにくく作業が複雑なため、値段が高くなります。
手作業の細かさによる九谷焼の価格相場の違い
九谷焼の値段は、手作業の細かさによっても価格が変動します。
価格相場が高い大皿のなかでも、おおらかな画風のものは比較的値段が低く、逆に細かい筆致で器全面に趣向を凝らした画風の作品は、値段が高くなります。
また、九谷焼はプリント(転写)の作品も多く発売されています。
それらの作品は、手作業を必要としないため、比較的値段が安いです。
九谷焼を安価に試したい方には、プリントの作品も良いですが、精密な手書きの美しさや、あたたかみに惹かれる方は、作家が描いた一点ものの作品をぜひ手にとってください。
九谷焼を普段使いして素敵な生活を送りましょう
九谷焼は、優雅さと実用性を兼ね備えた食器です。
九谷焼を普段使いすれば、今まで以上に充実した食事の時間が楽しめるでしょう。
器をレンタルして、もし飽きてしまったら送料無料で返却できますので、九谷焼初心者の方にも安心です。
レンタルした九谷焼が気に入ったので、このまま使い続けたい!という方は、5ヵ月利用を継続するとそのまま自分のものになります。その後は費用はかかりません。
普段の食事のシーンにあわせて、ぜひ素敵な九谷焼をチョイスしてくださいね。
\ 全品新品!1か月単位でお試しできる /
和食器をレンタルするなら「LIFT」